目指せ!第14回UEC杯コンピューター囲碁大会☆(^q^)<その6>
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
目指せ!第14回UEC杯コンピューター囲碁大会☆(^q^)<その6>
2022-09-22 thu 18:44

「 『連単位』であるとき、関心があるのは この連は、どの連と隣接しているか、
ということと、もうひとつあるぜ」

「 部屋の外で ピリリピリリ と鳴いているのは なんの虫だぜ?」

「 お父んさんの話しに 関心を持ちなさい」

「 説明しよう」
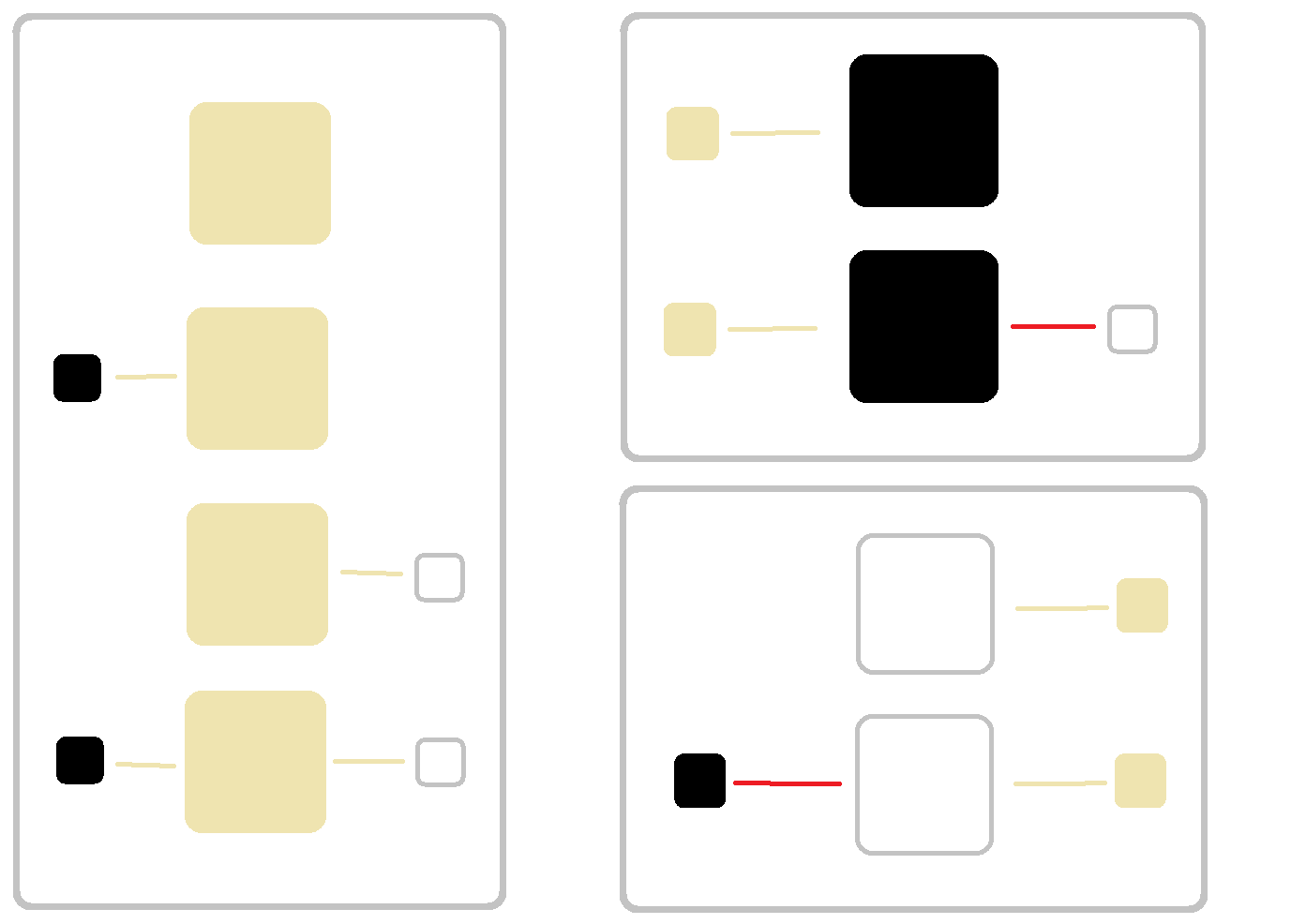

「 ↑ 初期局面だけ、空点だけがあり、何とも隣合わないというケースがある。
また、石には必ず 隣り合う空点がある」

「 石は 息 してるしな」

「 赤いエッジが 一番の関心事でしょ。
石が取られるかもしれない」

「 まだ話は続くぜ」
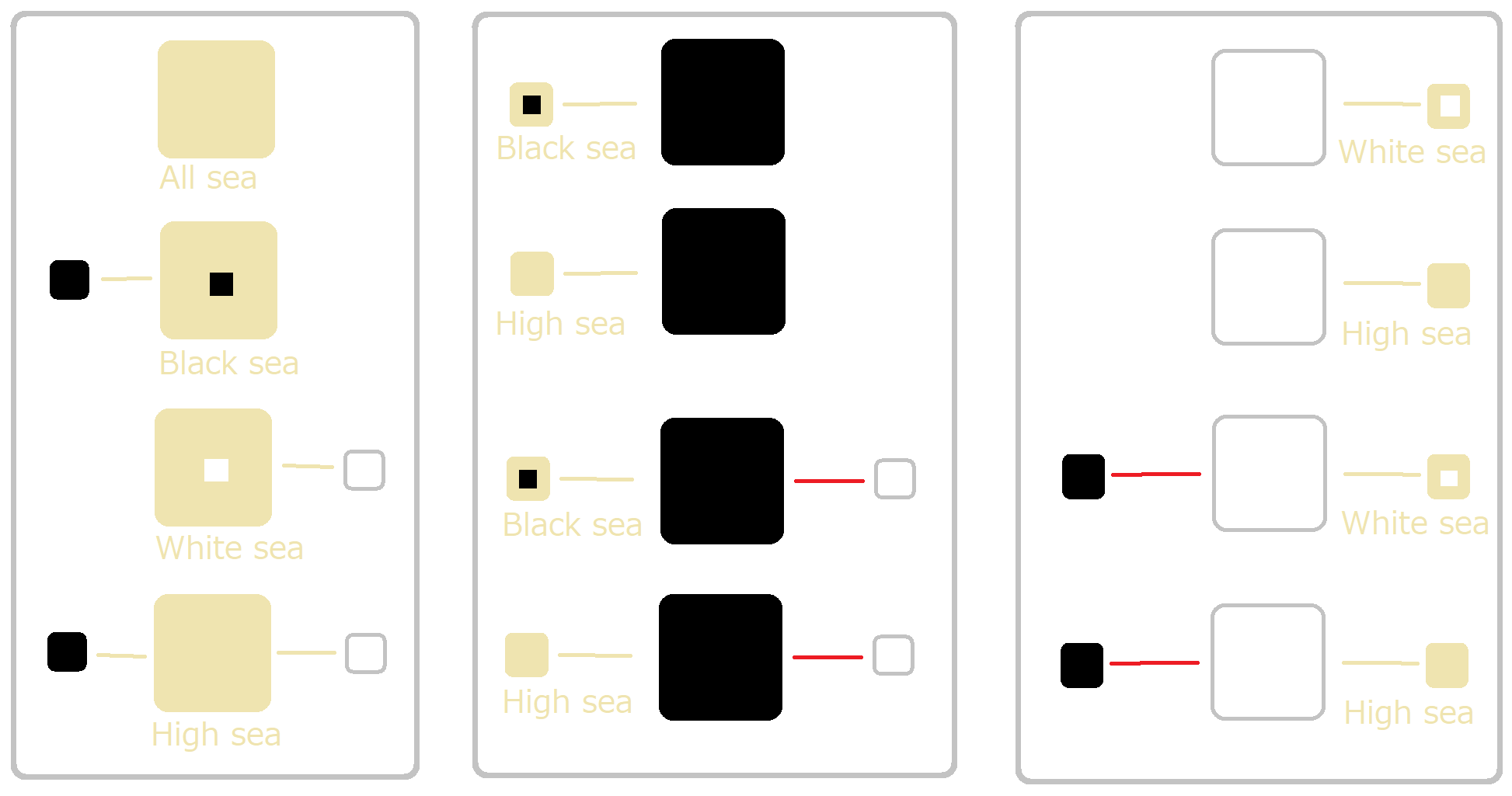

「 空点の連を、 『地』と呼ぶのではなく、
吉川竹四郎・著『コンピュータ囲碁GREAT』に倣って、『海』と呼ぼうぜ」

「 竹四郎の本では 海は SIMPLE、PRIVATE、PUBLIC の3種類で 意図も異なるぜ」

「 わたしがもっと大きな枠組みの中に SIMPLE、PRIVATE、PUBLIC を取り込み、
再構築する」
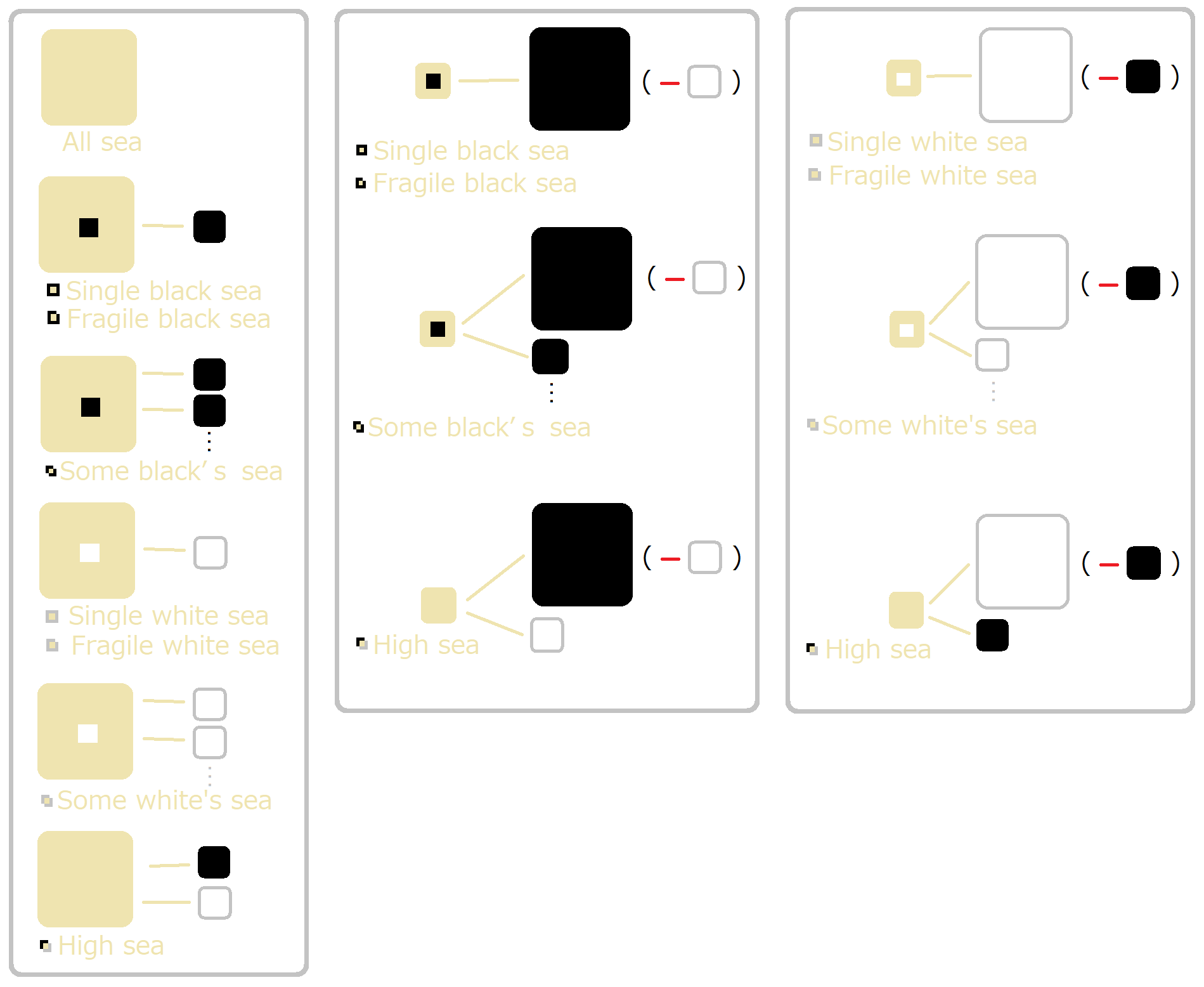

「 海は 8種類ある」

「 わらう」

「 囲碁盤の上は ほとんど High sea (公海)なんじゃないか?」

「 竹四郎の著書の2001年と違って、
現代には プレイアウト と モンテカルロ木探索 がある。
末端局面に行けば 公海は減るから 気にしなくていいぜ」

「 中国ルールなら そうなんでしょうけどね。
竹四郎の著書は 日本ルールと 中国ルールの両方で遊べるように 併せて書いてるのよ」

「 日本ルールは ばっさり 省こうぜ」

「 海って 簡易的な地計算の前段階だろ。
このあと Ray (レイ)を飛ばしたり、
竹四郎の Door(ドア)や Family(ファミリー)の考え方を取り入れて
黒と白は 何目差か 推定するんじゃないのかだぜ?」

「 モンテカルロ木探索に 何目差 とか必要ない。
全部ばっさりカットする」

「 横暴わらう」

「 中国ルールでプレイアウトして 投了図の石を数えるだけなら、
『海』という概念は要らないのでは?」

「 竹四郎の著書を捨てて 石を打つ、戻すのを高速化して
プレイアウトの回数を増やした方がよくない?」

「 要るときがくるまで 『海データベース』 要らないな」

「 要らないと思う」
2022-09-22 thu 23:07
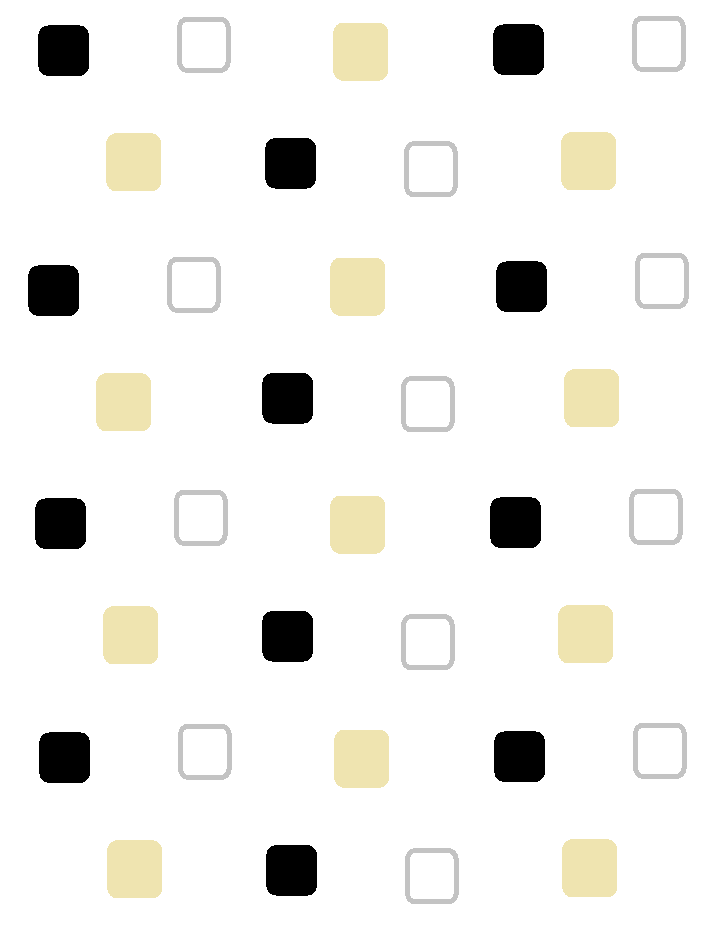

「 ↑ 『海』という概念が、さらにその上の 現在の私に認識できない上位概念への
道ができていないか 考えたろ。 名前は 『雲』 とでも名付けるかな」

「 足元を固めず 第6感で生きてるの わらう」

「 生物として 競争に生き残らないと思う」
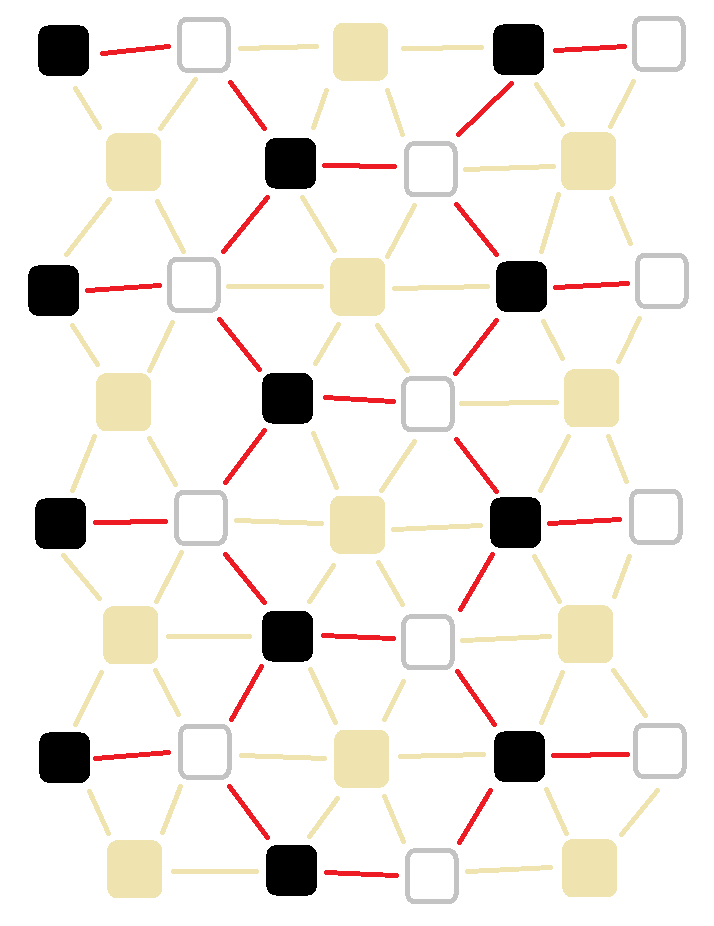

「 ↑ 全結合すると こうだが、結合が多すぎると思う」

「 エッジが1本の黒とか 白が あるんじゃないか?」
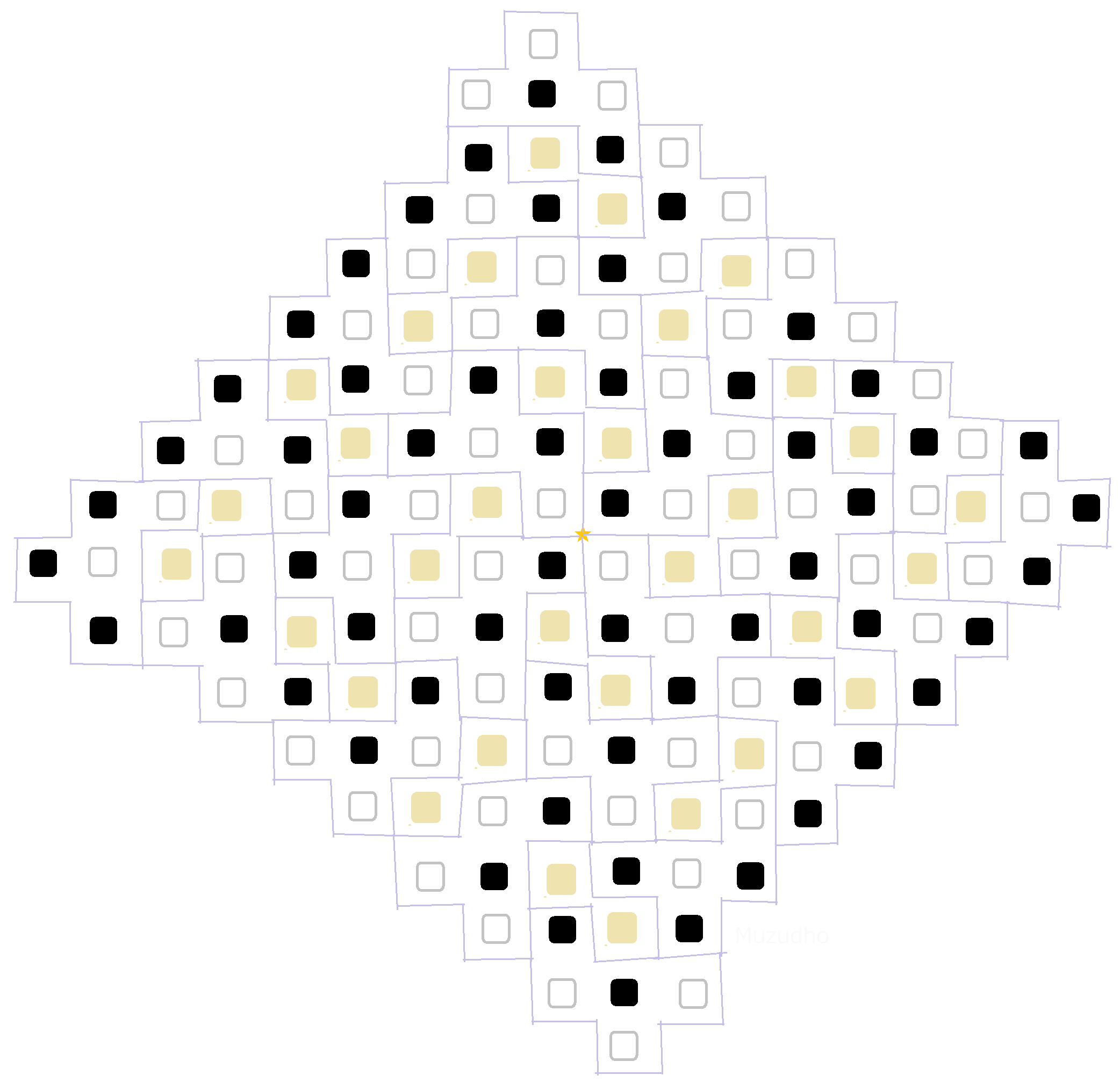

「 作品タイトル 雲の囲碁 だぜ」

「 空間充填 わらう」
「 『連単位』であるとき、関心があるのは この連は、どの連と隣接しているか、
ということと、もうひとつあるぜ」
「 部屋の外で ピリリピリリ と鳴いているのは なんの虫だぜ?」
「 お父んさんの話しに 関心を持ちなさい」
「 説明しよう」
「 ↑ 初期局面だけ、空点だけがあり、何とも隣合わないというケースがある。
また、石には必ず 隣り合う空点がある」
「 石は 息 してるしな」
「 赤いエッジが 一番の関心事でしょ。
石が取られるかもしれない」
「 まだ話は続くぜ」
「 空点の連を、 『地』と呼ぶのではなく、
吉川竹四郎・著『コンピュータ囲碁GREAT』に倣って、『海』と呼ぼうぜ」
「 竹四郎の本では 海は SIMPLE、PRIVATE、PUBLIC の3種類で 意図も異なるぜ」
「 わたしがもっと大きな枠組みの中に SIMPLE、PRIVATE、PUBLIC を取り込み、
再構築する」
「 海は 8種類ある」
「 わらう」
「 囲碁盤の上は ほとんど High sea (公海)なんじゃないか?」
「 竹四郎の著書の2001年と違って、
現代には プレイアウト と モンテカルロ木探索 がある。
末端局面に行けば 公海は減るから 気にしなくていいぜ」
「 中国ルールなら そうなんでしょうけどね。
竹四郎の著書は 日本ルールと 中国ルールの両方で遊べるように 併せて書いてるのよ」
「 日本ルールは ばっさり 省こうぜ」
「 海って 簡易的な地計算の前段階だろ。
このあと Ray (レイ)を飛ばしたり、
竹四郎の Door(ドア)や Family(ファミリー)の考え方を取り入れて
黒と白は 何目差か 推定するんじゃないのかだぜ?」
「 モンテカルロ木探索に 何目差 とか必要ない。
全部ばっさりカットする」
「 横暴わらう」
「 中国ルールでプレイアウトして 投了図の石を数えるだけなら、
『海』という概念は要らないのでは?」
「 竹四郎の著書を捨てて 石を打つ、戻すのを高速化して
プレイアウトの回数を増やした方がよくない?」
「 要るときがくるまで 『海データベース』 要らないな」
「 要らないと思う」
2022-09-22 thu 23:07
「 ↑ 『海』という概念が、さらにその上の 現在の私に認識できない上位概念への
道ができていないか 考えたろ。 名前は 『雲』 とでも名付けるかな」
「 足元を固めず 第6感で生きてるの わらう」
「 生物として 競争に生き残らないと思う」
「 ↑ 全結合すると こうだが、結合が多すぎると思う」
「 エッジが1本の黒とか 白が あるんじゃないか?」
「 作品タイトル 雲の囲碁 だぜ」
「 空間充填 わらう」
PR
コメント
プロフィール
HN:
むずでょ
性別:
非公開
最新記事
(01/21)
(11/23)
(11/04)
(10/13)
(09/22)
